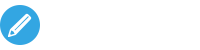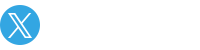目次
シリーズ1: シロアリ駆除ってどんなサービス?
「シロアリ駆除」という言葉を耳にしたことがあっても、具体的に何をするサービスなのか詳しく知らない方も多いのではないでしょうか?
今回は、シロアリ駆除の基本について分かりやすくお話しします!
1. シロアリってどんな害虫?
シロアリは木材を主食とする害虫で、私たちの家に大きな被害をもたらします。
特に床下や壁の内部、見えにくい場所で活動するため、気づかないうちに家の構造が危険な状態になっていることも…。
以下の特徴がシロアリの厄介なポイントです:
- 見えにくい場所で活動:床下や壁の中など、目に見えないところで木材を食害します。
- 湿気を好む:特に湿気の多い場所に発生しやすく、湿度の高い地域や梅雨時期は要注意。
- 家全体に影響:柱や梁が弱くなると家の耐震性が低下する可能性があります。
2. シロアリ駆除とは何をするの?
シロアリ駆除は、発生したシロアリを駆除するだけでなく、再発を防ぐための予防対策も含まれるサービスです。
以下の2つの主要な対応方法があります:
- 予防
新築時や定期点検の際に行う、これからのシロアリ発生を防ぐ対策です。薬剤の塗布やバリア工法などが用いられます。
- 発生駆除
すでにシロアリが発生している場合に行う駆除作業です。特殊な薬剤やベイト(毒餌)を使用して巣ごと駆除します。
3. シロアリ駆除・予防が必要な場面
シロアリ駆除は、以下のようなタイミングで利用されることが多いです:
- 新築時の予防対策
家を建てるときに予防処置を行うことで、将来的なシロアリの被害を防ぎます。
- 中古住宅購入後の点検
購入した住宅が以前シロアリ被害を受けていたかどうか、また現在の状態を確認するための点検が重要です。
- 床下や壁の傷みが見つかったとき
例えば、床を歩いたときにフカフカしていたり、壁に空洞音がする場合はシロアリ被害の可能性があります。
4. シロアリ駆除・予防のメリット
シロアリ駆除を行うことで、以下のようなメリットがあります:
- 家の寿命が延びる
シロアリ被害を未然に防ぐことで、家の構造を長く保てます。
- 安心して暮らせる
シロアリの心配がなくなることで、家族全員が安心して過ごせます。
- 資産価値の維持
シロアリ被害がない家は資産価値が高く、将来的な売却時にも有利です。
次回予告!
次回は「シリーズ2: シロアリ被害の見分け方」をお届けします。
シロアリ被害を早期に発見するためのポイントを、分かりやすく解説します!